

ブゲン
どうもブゲンです!たまむら歌留多巡りやっていくよ♪

ブゲン
今回紹介する札は…「せ」の札だよ!

ブゲン
関流の和算の奇才宜長宜義っていう札なんだ!
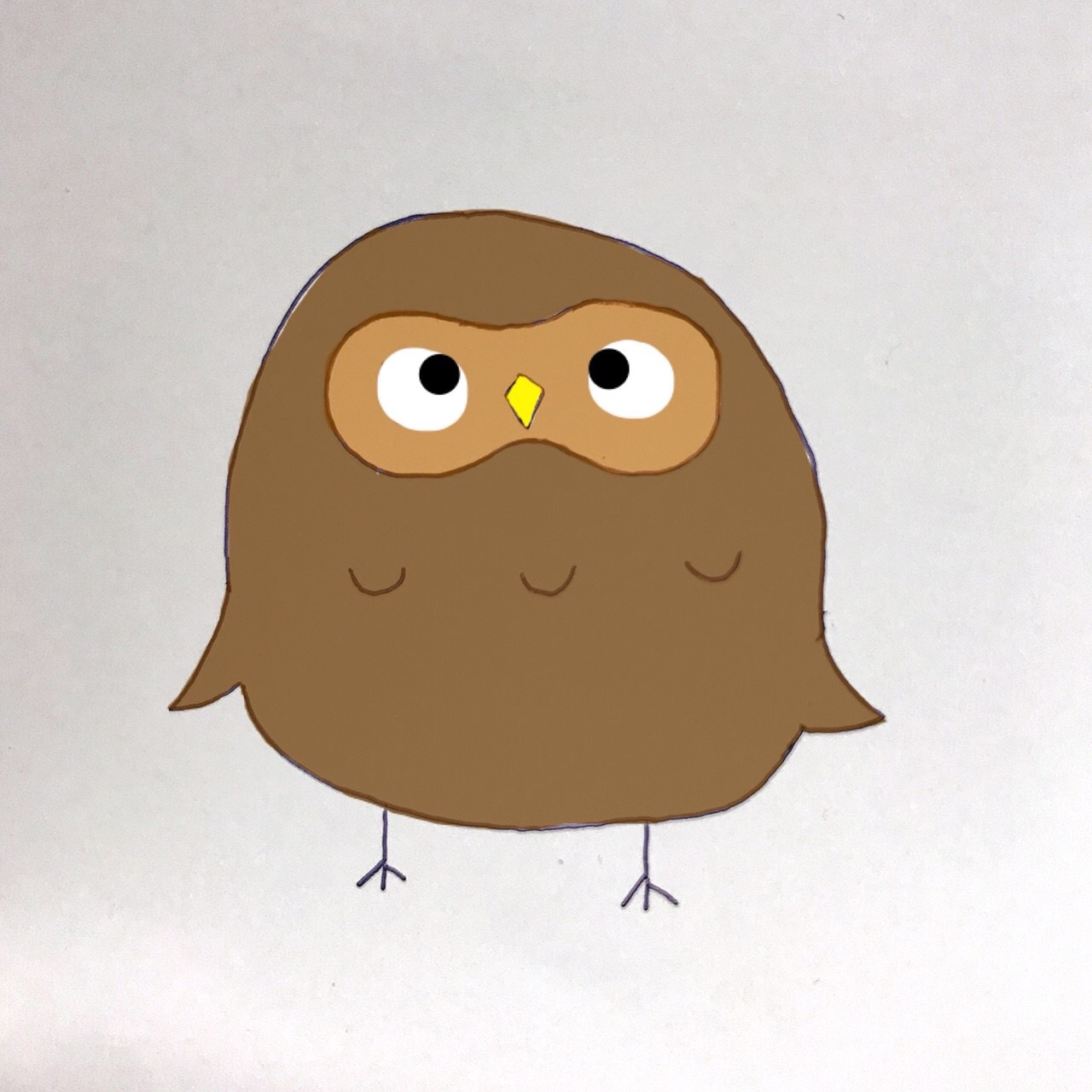
ふく老師
関流?和算?まさか…

ブゲン
よく気付いたね!上毛かるたでおなじみの【ある人物】に関連している札でもあるんだ!
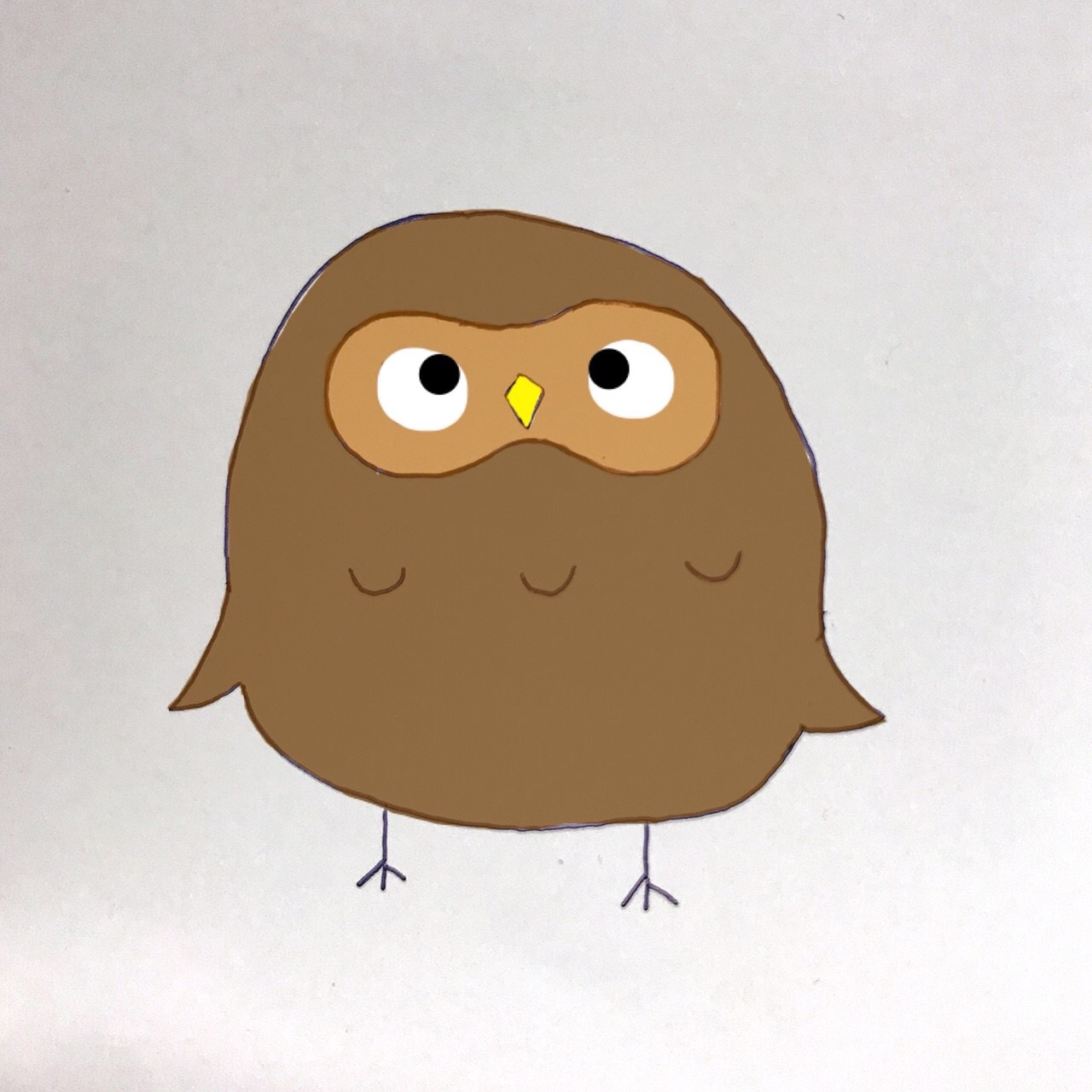
ふく老師
たまむら歌留多と上毛かるたが繋がったのぉ…

ブゲン
そうだね♪さっそく調べていこう!
スポンサーリンク
関流の和算とは!?
 まず最初に、関流の和算とは一体どういったものでしょうか?
まず最初に、関流の和算とは一体どういったものでしょうか?
群馬県民の方は上毛かるた「わ」の札「和算の大家関孝和」で和算という言葉は知っているかと思います。
和算とは中国算法の流れを受け、日本独自に発展した数学のことです。
江戸時代以降に関孝和による理論や組み立て式が知られ、発展することで、関流の和算が全国的に広まっていきました。
どういった数学なのかは検索すると出てくるので調べてみてください。

ブゲン
算数とか数学とかよく分かんないや♪
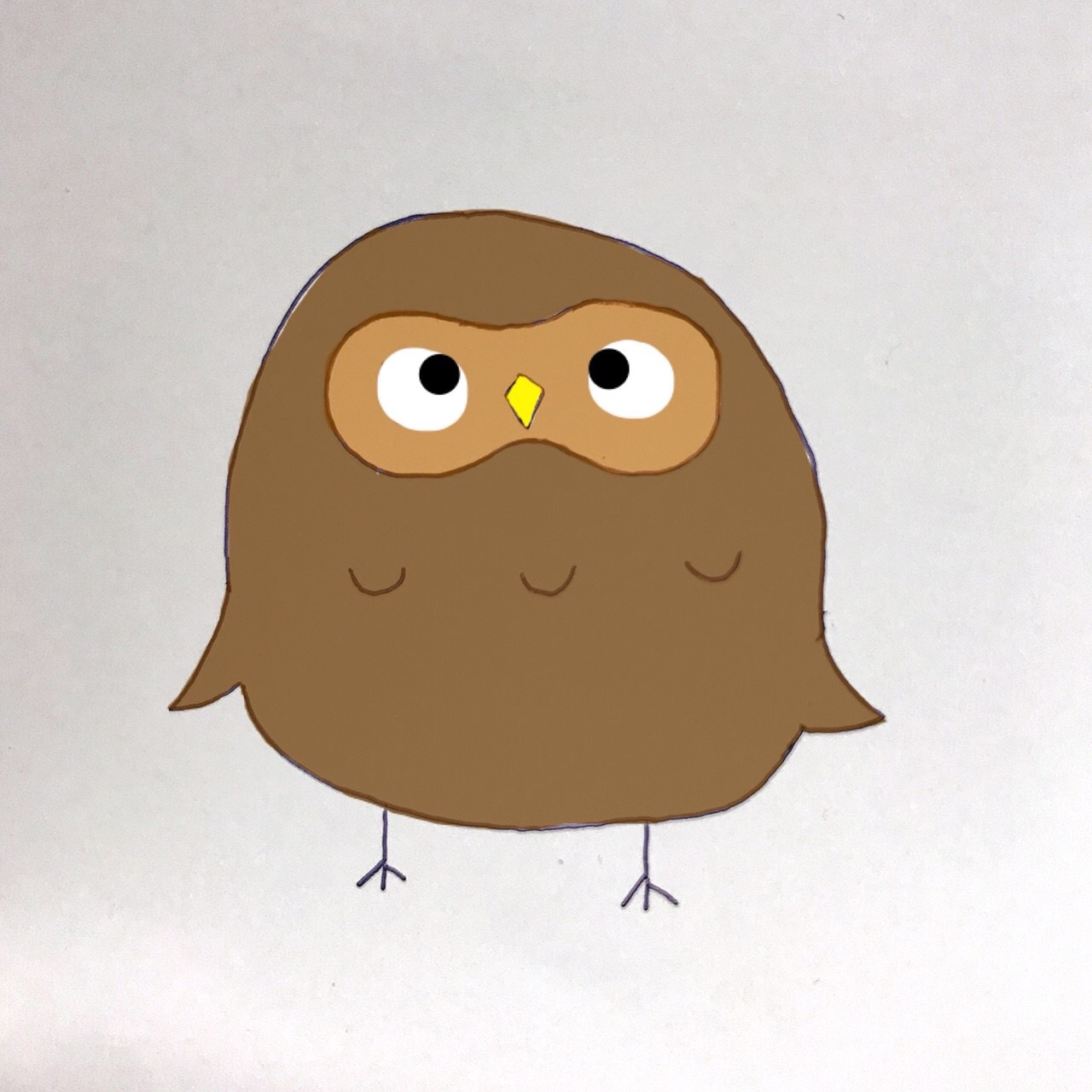
ふく老師
コラコラ…
それでは、札に書かれている斎藤宜長・宜義という人物について調べていきましょう。
斎藤宜長・宜義とは?

巡ってる時に気付かなかったのですが、札に書かれている宜長宜義は一人の人物の名前ではありません笑
父の斎藤宜長と息子の宜義という親子の名前だったのです。

ブゲン
宜長宜義っていう人がいるのかと思ったよ!
たまむら歌留多巡りのMAPに記されていたのは玉村町坂井にある「宝蔵寺」です。
こちらのお寺に、2人のお墓があります。

残念ながらご住職にお話を聞くことはできませんでしたが、お墓の横に看板が建てられていました。
紹介していきます。
斎藤宜義は、関流(八代目)の和算の大家です。和算とは、江戸時代に関孝和により創始された日本独自の数学のことです。
文化十三年(一八一六年)群馬県滝川村坂井(現玉村町)に、斎藤宜長の次男として生まれた宜義は、父とともに天下に上毛の算者と云われ、特に「円理」と呼ばれた現在の微積分の研究にすぐれた業績を残しました。その代表的な著書として、「算法円理起源表」や、「円理新々」などがあります。また、玉村八幡宮や高崎市石原清水観音堂に奉納した算額も現在に伝えられています。
宜義は、明治二十二年(七十四才)でこの世を去りましたが、多くの弟子たちのなかには、和算の最後の大家として知られる萩原禎助や、日本三老農のひとり船津伝次平がいたことが知られており、これら弟子たちの活躍は和算に限らず、郷土文化発展の歴史の上でそれぞれ大きな足跡を残しています。
引用元:群馬県教育委員会/玉村町教育委員会
文化十三年(一八一六年)群馬県滝川村坂井(現玉村町)に、斎藤宜長の次男として生まれた宜義は、父とともに天下に上毛の算者と云われ、特に「円理」と呼ばれた現在の微積分の研究にすぐれた業績を残しました。その代表的な著書として、「算法円理起源表」や、「円理新々」などがあります。また、玉村八幡宮や高崎市石原清水観音堂に奉納した算額も現在に伝えられています。
宜義は、明治二十二年(七十四才)でこの世を去りましたが、多くの弟子たちのなかには、和算の最後の大家として知られる萩原禎助や、日本三老農のひとり船津伝次平がいたことが知られており、これら弟子たちの活躍は和算に限らず、郷土文化発展の歴史の上でそれぞれ大きな足跡を残しています。
引用元:群馬県教育委員会/玉村町教育委員会

ブゲン
関孝和さんに船津伝次平さんまで…!
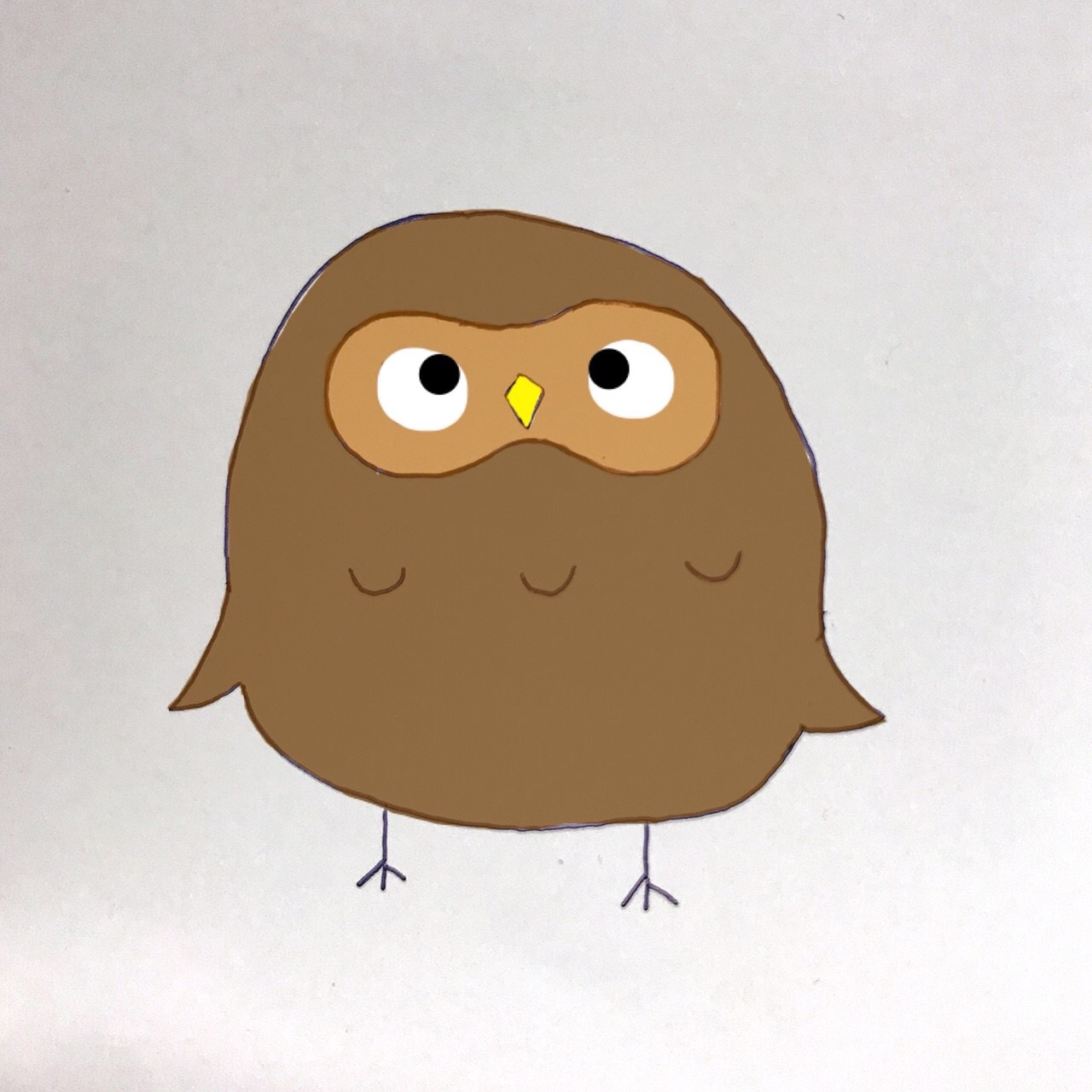
ふく老師
関流を学び、それを後世に広めていったんじゃな…

ブゲン
難しいことわかんないけど、上毛かるたに登場する人がたくさん出てきて嬉しいな~♪
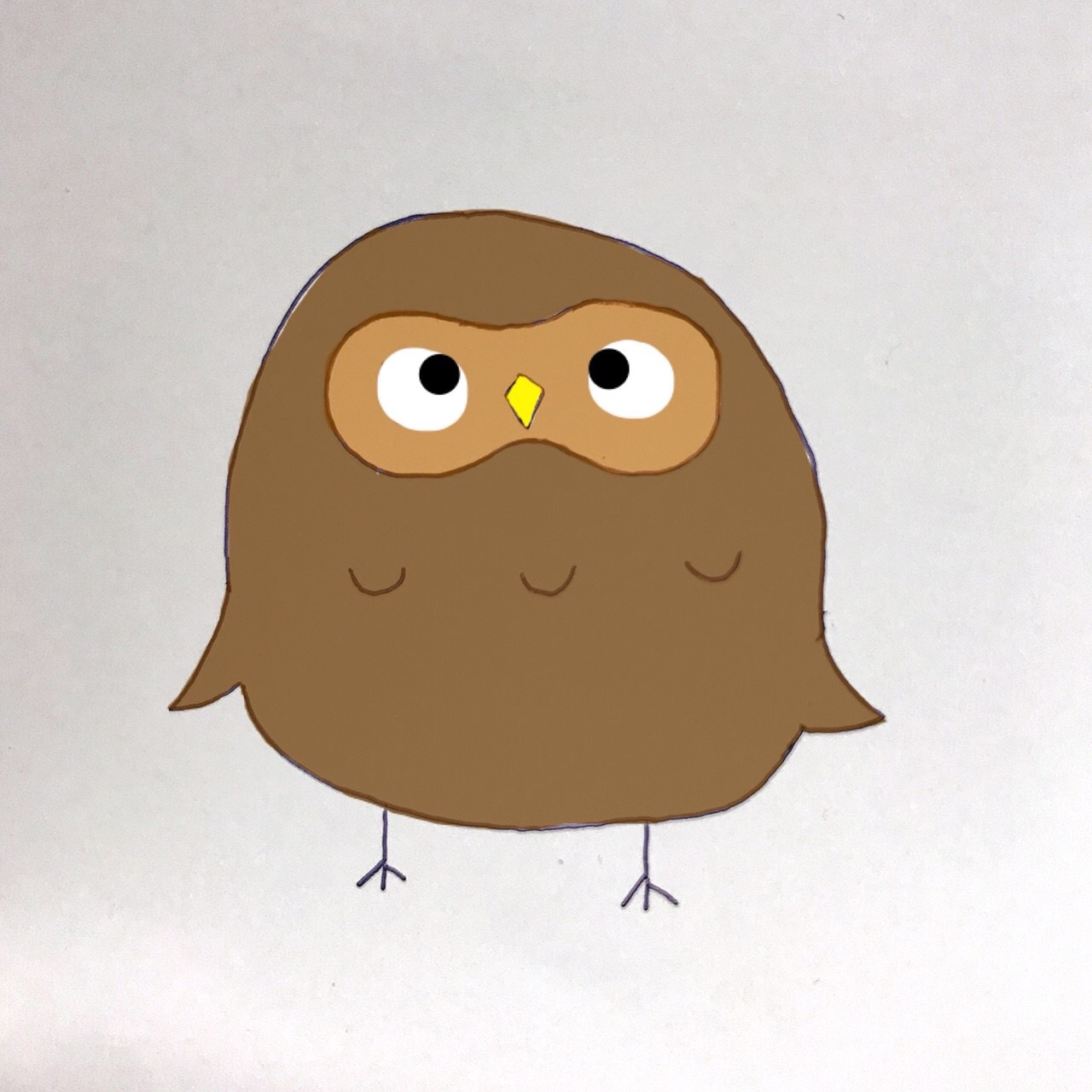
ふく老師
まったくブゲンは…
アクセス
住所:

